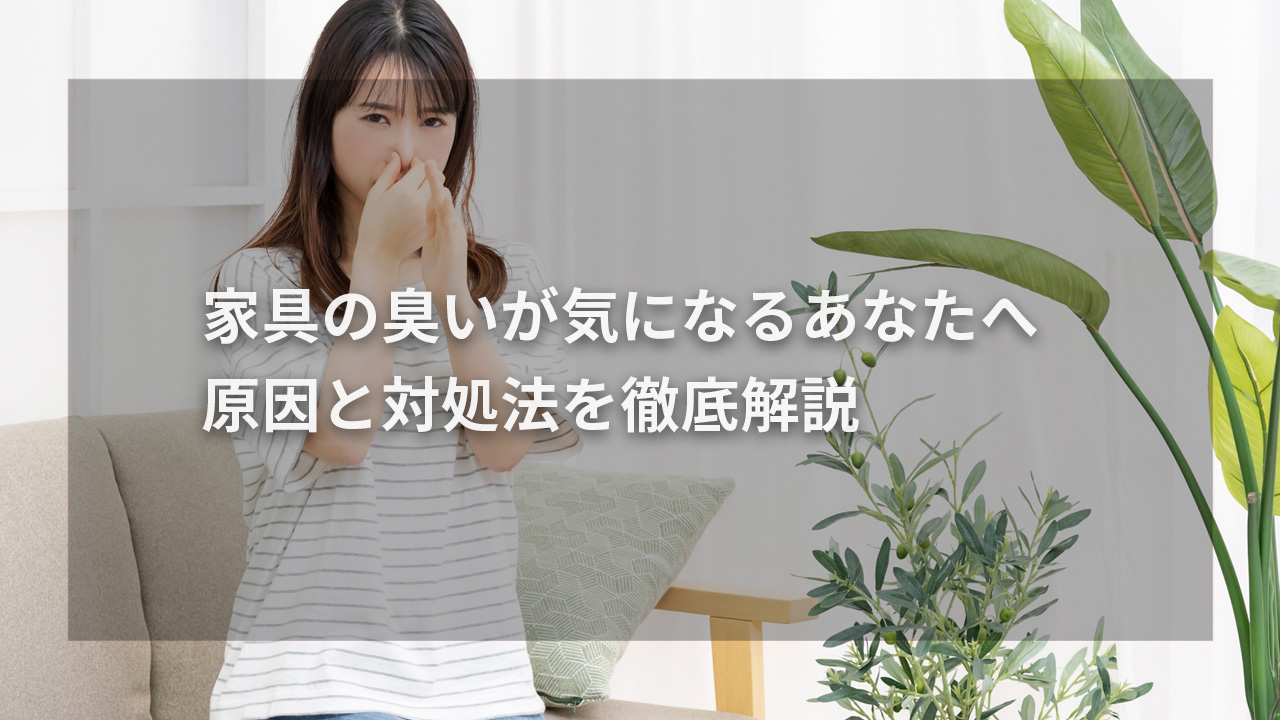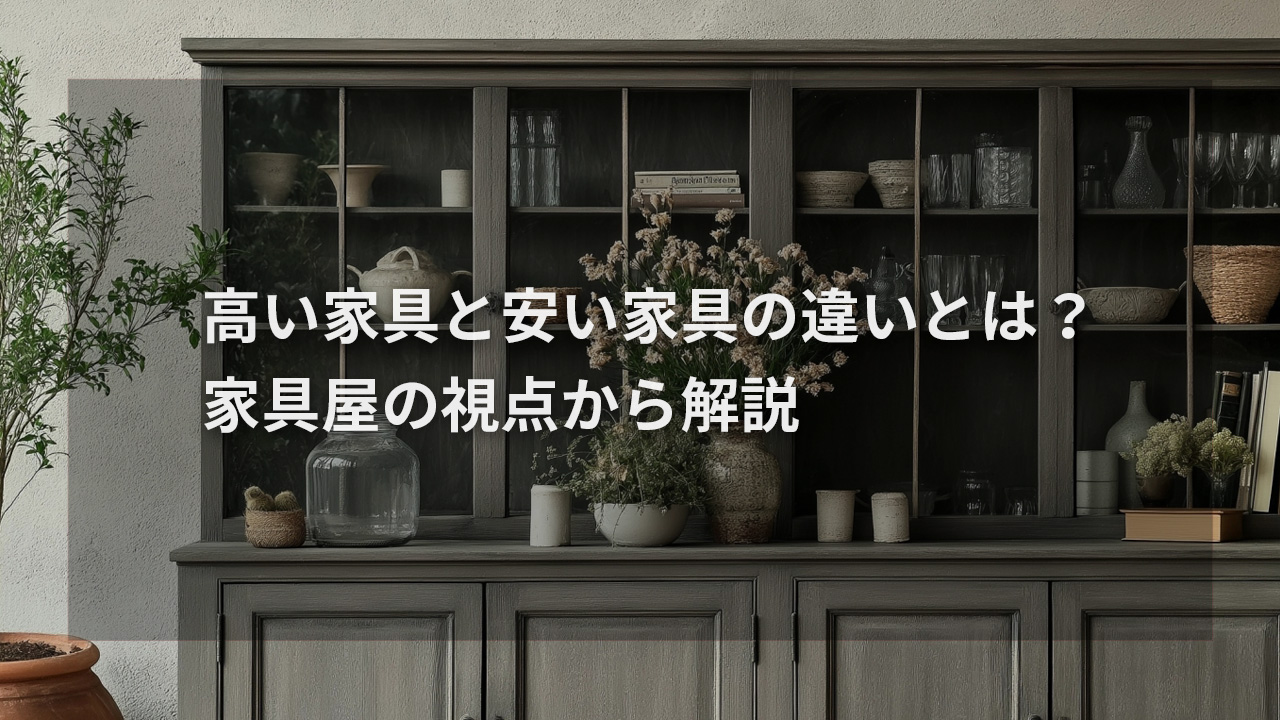間伐材とSDGs:森林を守るために私たちができること

日本の森林は、私たちの生活に欠かせない自然資源ですが、近年その手入れが行き届かず、土砂崩れや環境破壊が進んでいます。
そこで重要なのが「間伐材」の活用です。
間伐材は、森林を健全に保つために必要な作業であり、エコな選択肢でもあります。
間伐を適切に行うことで、土砂崩れの防止や水源の保護、さらにはSDGs(持続可能な開発目標)への貢献にもつながります。
この記事では、間伐材の役割やその重要性について詳しく解説します。
▼目次
1.日本の森林の現状と私たちの暮らし
日本の森林の現状と役割
人工林と林業の衰退
間伐と森林の健全性
2.間伐とは?なぜ必要なのか
森林の健全な成長と生物多様性の維持
木々の成長促進と質の良い木材の生産
水源保全と環境保護
持続可能な林業と地域社会への貢献
3.間伐をしないとどうなる?
土砂崩れのリスクが高まる
健康な木が育ちにくくなる
水源の枯渇
経済的な影響
4.戦後の杉植林とその影響
なぜ杉が大量に植えられたのか?
花粉症問題との関係
5.間伐材の活用が未来を変える
間伐材の特性と多様な活用法
バイオマスエネルギーとしての活用と環境負荷の削減
地域経済への貢献と持続可能な社会の実現
1.日本の森林の現状と私たちの暮らし
日本の森林の現状と役割
日本は国土の約7割が森林に覆われていますが、その多くは適切に管理されていないのが現状です。
特に、戦後に急速に木材生産を目的として植えられた杉やヒノキなどの人工林は、長年の手入れ不足で健康状態が悪化しています。
これらの人工林は、四季折々の美しい風景を生み出し、自然環境の保護にも寄与する役割を担っていますが、現在では森林の管理が行き届いていないため、その重要な機能が十分に発揮されていない状況です。
日本の森林は、ただの景観や自然の一部ではなく、水源保全や土壌保護、さらには二酸化炭素の吸収など、私たちの生活を支える不可欠な要素としても重要な役割を果たしています。
これらの機能を維持するためには、森林の健全な管理と手入れが必要不可欠です。
人工林と林業の衰退
人工林は特定の樹種を計画的に植え、木材の収穫を目的とした森林です。
日本では、戦後の木材不足や復興のために急速に人工林が広がりましたが、これらの森林は主に杉やヒノキなどの速成型の樹種が多く、管理が十分でないため、現在では多くが健全な状態を欠いています。
一方、天然林は自然に育った森林で、多様な樹種が共生しています。
人工林の急増は、戦後の木材需要を満たすためでしたが、現代においてはこれらの人工林が適切な管理を受けずに放置されていることが問題となっています。
これにより、森林の質が低下し、木材生産にも支障をきたす状況となっています。
さらに、林業は木材価格の低下や、若い世代の従事者不足、過剰な伐採などにより深刻な危機に直面しており、その結果、持続的な森林管理が難しくなっています。
間伐と森林の健全性
間伐は森林の健康を保つために、過剰に成長した木を伐採し、残りの木に十分な光と栄養を供給する作業です。
これにより、森林が多様性を維持し、生物多様性の保護にも繋がります。
また、間伐によって、木々の根が広がり、土壌の安定性が向上するため、豪雨や台風などの際の土砂災害リスクを軽減できます。
手入れが行き届いていない森林では、木々が密集しすぎて根が広がらず、土壌が不安定になりやすいです。
そのため、土壌が流失しやすく、山崩れや土砂災害が発生するリスクが高まります。
間伐を進めることは、森林の健全性を保つために非常に重要であり、山を守ることが私たちの安全を守ることにも直結しています。
森林の適切な管理と間伐が進めば、土壌の流出を防ぎ、災害リスクを減少させることが可能です。

山を守ることは、私たちの安全を守ることでもあるのです。
そのために重要な役割を果たすのが「間伐」です。
2.間伐とは?なぜ必要なのか
間伐は、森林の健全な成長を促進し、持続可能な森林利用を実現するために欠かせない作業です。
間伐とは、森林の中で過剰に成長した木々を計画的に伐採することによって、残された木々に十分な光、栄養、水分を与え、森林の健康を保つための方法です。
森林は単に木が密集して生えている場所ではなく、複雑な生態系として成り立っています。
その中で間伐は、木々の成長に必要なスペースを作り、バランスの取れた森林環境を維持するために重要な作業です。
森林の健全な成長と生物多様性の維持
森林の木々は成長の過程で光を求めて競争しますが、過密状態になると光が地面に届かず、下草が育たなくなります。
その結果、土壌がむき出しになり、保水力が低下して土砂崩れのリスクが高まるほか、植物の生育が阻害され、生物多様性が損なわれます。
森林の健全性を保つためには、適切な間伐が不可欠です。
間伐を行うことで、木々の間に適度なスペースが生まれ、日光が地面に届くようになります。
その結果、下草や低木が育ちやすくなり、さまざまな動植物が生息できる環境が整います。
また、風通しが良くなることで湿度が調整され、病害虫の発生が抑えられます。
特に、希少な植物や動物が生息する森林では、間伐が生態系の維持に重要な役割を果たします。
木々の成長促進と質の良い木材の生産
過密な森林では、木々が十分な栄養や水分を吸収できず、細いまま弱々しく成長したり、最悪の場合枯れてしまうことがあります。
また、光や空気の供給が制限されるため、木々の健全な成長が妨げられます。
適度な間伐を行うことで、木々は互いに競争せず、残された木々がより太く丈夫に成長することができます。
間伐後に健全に育った木々は、強度があり、質の良い木材として利用されることが多くなります。
そのため、木材業界にとっても間伐は重要な要素となります。
適切に管理された森林では、高品質な木材を持続的に生産でき、林業の発展にも寄与することができます。
水源保全と環境保護
森林は水源の保全にも重要な役割を果たします。
木々が土壌を保護し、水を吸収することで、降雨時に水源が急激に増えることを防ぎ、地下水の蓄積を促します。
しかし、森林が健康を損なうと、この水源保全機能も失われてしまいます。
適切な間伐により、土壌の水分が適切に調整され、雨水が地下に浸透しやすくなります。
その結果、土砂崩れのリスクが軽減され、河川の水質悪化を防ぐことができます。
また、森林が健全であれば、二酸化炭素の吸収能力が向上し、地球温暖化防止にも寄与します。
間伐によって森林の環境保全機能を高めることは、持続可能な社会の実現にもつながるのです。
持続可能な林業と地域社会への貢献
間伐は持続可能な林業を実現するために不可欠な作業です。
適切な間伐を行うことで、森林の健康を保ちつつ、次世代の森林資源を確保しながら木材を供給することが可能になります。
また、間伐によって得られた木材は、家具や建材などさまざまな用途で利用され、経済的な価値を生み出します。
さらに、森林が健全であれば、林業が活発になり、地域経済の発展にも貢献します。
間伐が適切に行われることで、森林資源が持続的に活用でき、長期的な視点でも安定した経済基盤を築くことができます。
森林と林業が共に発展することで、環境保全と経済発展の両立が可能となるのです。

3.間伐をしないとどうなる?
土砂崩れのリスクが高まる
森林がその役割を果たすためには、木々が地面にしっかりと根を張り、土壌をしっかりと支えることが不可欠です。
間伐を行わず、木々が密集したまま放置されると、下草や低木が育たず、土壌がむき出しになってしまいます。
特に、急傾斜地や山間部では、土壌がむき出しになることで、雨が降った際に土壌が流されやすくなり、土砂崩れや洪水のリスクが高まります。
例えば、2017年に発生した広島県の豪雨災害では、大規模な土砂崩れが発生しました。
この土砂崩れの原因として、間伐が十分に行われていないことが挙げられました。
過密状態にあった森林では、根の張りが不十分で、豪雨によって土壌が流れ出し、結果的に家屋の倒壊や人命の喪失など、大きな被害を引き起こしました。
このように、間伐が行われないことが直接的に土砂災害を引き起こす原因となることがあるのです。
また、間伐を行うことで、木々の根がよりしっかりと土壌を支えることができ、土壌の流出を防ぐ効果があります。
適切な間伐によって、地面に十分な光が届き、下草や低木が育ち、森林全体が健全な状態を保つことができます。
その結果、豪雨が降っても土壌が流れにくくなり、土砂崩れのリスクを減らすことができるのです。
健康な木が育ちにくくなる
木々が密集して成長すると、それぞれの木が必要とする光や養分が十分に得られなくなります。
特に若い木は、成長するために十分なスペースを確保できず、枝葉を広げることができません。
その結果、木は細く、弱々しいものばかりになり、病害虫の被害を受けやすくなります。
また、過密状態の森林では、樹木の成長が鈍化し、健康的な木が育つために必要な栄養分を得ることができません。
このような環境では、木々の根が十分に張ることができず、栄養や水分が効率的に供給されません。
特に、木々が競い合って成長する中で、弱い木がしばしば育ち、最終的には枯れてしまうことがあります。
実際に、北海道のある地域では、過密状態の森林が原因で、樹木が育たず、森林の質が低下している事例が報告されています。
この地域では、森林に十分な間伐が行われていないため、木々の間隔が狭く、日光が届かず、健康な木が育ちにくくなっていました。
そのため、木々の間に空間を作り、日光を十分に当てることが求められました。
間伐によって空間を確保することで、残された木々が健康に育つことができるのです。
また、間伐によって強い木が残ると、病害虫の発生が抑制されることにもつながります。
間伐作業が適切に行われた結果、木々が十分に栄養を得ることができ、病害虫による被害を最小限に抑えることができるのです。
これは、森林全体の健康を保つために重要な要素となります。
水源の枯渇
森林は、二酸化炭素の吸収や酸素の供給だけでなく、地下水の養成にも重要な役割を果たしています。
健康な森林は、雨水を吸収して地下水に蓄え、乾季においても安定した水供給を維持します。
しかし、間伐が行われていない森林では、木々が過密状態となり、根の張りが不十分になるため、水分の吸収効率が低下します。
その結果、地下水が十分に蓄えられなくなり、最終的には水源の枯渇を招くことがあります。
例えば、宮崎県のある地域では、間伐が十分に行われていなかったため、降雨後の水の浸透が悪くなり、地下水位が急激に低下しました。
この地域では、特に夏場の乾燥が深刻で、農業における水源の不足が問題となっていました。
間伐を行い、森林の健康を保つことによって、地下水位を安定させることが求められました。
間伐を通じて森林の根がしっかりと土壌に浸透し、地下水を蓄える能力が回復するため、地域全体の水源の安定供給が期待できるのです。
また、間伐が行われた森林では、水源の枯渇を防ぐだけでなく、水質の向上にもつながります。
森林が健全であれば、雨水が浸透しやすくなり、地表面から直接水が流れることを防ぎます。
これにより、川や湖の水質が保たれ、地域の生態系が守られることになります。
経済的な影響
間伐をしないことで、長期的には森林資源の利用効率が低下し、経済的な損失が生じることもあります。
森林は木材や薪、竹など、さまざまな資源を提供しており、これらは地域経済にとって重要な収入源となっています。
しかし、間伐が行われない森林では、木材の品質が低下し、木材としての価値が減少します。
また、森林が過密状態になれば、木材の成長も遅くなり、収穫するまでの時間が長くなってしまいます。
一方、間伐を適切に行うことで、木材の品質が向上し、販売価格も高くなる可能性があります。
間伐によって健康な木を育てることができ、その木々は家具や建材として利用されることが多いため、木材業界にも好影響を与えるのです。
さらに、間伐材を活用した製品の開発が進むことで、地域経済が活性化すると考えられます。
4.戦後の杉植林とその影響
なぜ杉が大量に植えられたのか?
戦後、日本の国土は戦争の影響を大きく受けていました。
特に、都市の再建やインフラの復旧のためには、大量の木材が必要とされました。
しかし、戦前の日本では、木材を輸入することが困難であり、国内の森林資源は不足していました。
このため、政府は木材の安定供給を目指し、人工林の造成を推奨しました。
その中で、杉(スギ)とヒノキは、日本の風土に適した樹種とされ、特に杉の植林が積極的に行われることになりました。
1950年代初頭、戦後復興のために国は「国土の緑化」という政策を掲げ、大規模な森林造成計画が始まりました。
この頃、杉の植林が広がりを見せるようになった背景には、杉が比較的早く成長し、木材としての用途が多岐にわたることが挙げられます。
杉の木材は軽くて強度があり、建築用材として非常に重宝されました。
また、木材の需要が急速に高まる中で、杉はその成長の速さからも非常に有用とされ、各地で植林が行われました。
さらに、当時の技術では、杉の人工林を管理するためのノウハウが乏しく、植林してしまえばあとは放置してもある程度育つという考えが広まりました。
植えられた杉は、戦後復興に貢献する「緑の宝庫」として期待されました。
しかし、その植林のペースは非常に速く、管理体制の整備が追いつかなかったため、次第に杉の人工林が過密状態になり、森林のバランスが崩れていったのです。
1950年代から1970年代にかけて、杉やヒノキの植林がピークに達し、約30年間にわたって急速に増加しました。
特に1960年代後半から1970年代前半にかけては、杉の植林が全国的に進み、その後の経済成長を支えるための木材供給源として重要な役割を果たしました。
しかし、問題はこの時期に植えられた杉の多くが、十分な手入れがされないまま放置され、人工林として本来の役割を果たすことができなかったことにあります。
その結果、現在では過密な人工林が広がり、杉の木々が健康に育たなくなり、森林の生態系に悪影響を与えるようになっています。

花粉症問題との関係
杉の大量植林は、私たちの健康にも大きな影響を与えることになりました。
特に春先に飛散するスギ花粉は、日本全国で深刻な問題となっています。
戦後の急速な杉の植林が進んだ結果、現在ではスギ花粉症に悩まされる人々が非常に多く、その影響を痛感している人々も少なくありません。
スギ花粉症の問題は、1960年代から1970年代にかけて顕著に現れるようになりました。
これは、戦後に植えられた杉の木々が成長し、花粉を大量に飛散させるようになったためです。
日本の杉は、春になると大量の花粉を飛ばし、特に風の強い日や気温が上昇すると、その飛散量が急増します。
この花粉が鼻や目に入ることで、花粉症を引き起こし、多くの人々が春先に苦しむことになったのです。
ある地域では、戦後に植えられた杉の木が生長するにつれて、毎年の花粉飛散量が増え続けるという状況が続きました。
特に、1970年代から1980年代にかけて、花粉症が広がり始め、多くの人々がその症状に悩まされるようになりました。
症状は、くしゃみや鼻水、目のかゆみだけでなく、ひどくなると呼吸困難や頭痛を引き起こすこともあり、生活に大きな支障をきたしました。
この花粉症問題は、単に健康面の問題だけでなく、社会や経済にも影響を及ぼしました。
病院には花粉症の患者が殺到し、薬の需要が急増しました。
また、企業や学校では、花粉症対策としてマスクを着用したり、外出を控えるなどの対策が必要となり、社会全体でその影響を受けることとなりました。
さらに、花粉症対策にかかる医療費や、薬の売上が急増する一方で、労働生産性の低下や、外出を控えることによる経済的な損失も発生しました。
例えば、ある企業では、社員の多くが春先に花粉症の症状を訴えるようになり、業務効率が低下したため、従業員に対して花粉症対策を講じる必要がありました。
花粉症に悩まされる社員には、特別な休暇を設けることを検討する企業も現れるなど、社会全体で花粉症に対処しなければならない状況となりました。
また、花粉症の影響は年々悪化しており、花粉の飛散量が増え続ける一方で、杉の木の花粉飛散ピークが長期間続くようになったため、対策が追いつかなくなっている現状もあります。
政府や自治体、企業は、杉の植林を見直すとともに、花粉症の予防や治療のための啓発活動を行ってきましたが、杉植林がもたらした花粉症問題は依然として解決されていない状況です。

5.間伐材の活用が未来を変える
間伐は、森林の健全な成長を促進するために非常に重要な作業ですが、その過程で伐採される木々を「間伐材」と呼びます。
間伐材は、一般的に市場価値が低いため、その多くが有効に活用されないまま放置されることが多いのが現状です。
しかし、近年ではこの間伐材が家具や建材、さらには紙やバイオマスエネルギーの原料として、持続可能な社会のために積極的に活用されるようになっています。
間伐材の適切な利用は、森林の健全な管理だけでなく、私たちの生活にも良い影響を与える可能性があるのです。
この章では、間伐材の利用がどのようにして未来を変えるのか、またその可能性を広げるためには何が必要なのかを探っていきます。
間伐材の特性と多様な活用法
間伐材は、成長の遅い木々や密集して育った木々の中から伐採されるため、その多くは比較的小さく、曲がりくねっていることが特徴です。
こうした木材は、強度や質の面で大きな木材と比べると見劣りしますが、だからこそ特別な用途において非常に有用な資源となります。
一部の間伐材は、家具や建材に使われることが増えてきています。
例えば、無垢材として利用される間伐材は、一般的な集成材とは異なり、木本来の質感や温かみを持っているため、特に自然素材を重視するインテリアや家具において人気があります。
また、間伐材の中には、木材の色味や模様が独特で、個性的なデザインを求める消費者にも好まれることが多いのです。
無垢材の家具や建材は、その耐久性にも定評があり、長年使い込むことで、木が味わい深く変化していくため、エコな生活を意識する人々にも好まれます。
さらに、間伐材は紙やパルプ製品の原料としても活用されています。
木材は紙の原料として長い歴史を持ち、間伐材は紙や段ボールなどの製品に加工されることが多いです。
間伐材はその性質上、細かく均一な繊維を作り出すことができるため、品質の高い紙を作ることが可能です。
また、環境配慮型のパッケージとして間伐材を使用した紙や段ボールの活用が広がっており、リサイクル可能な製品として循環型経済の構築にも貢献しています。
杉の間伐材を製材し、組手の形に加工したパーツ「組手什」。
自由な形に組み合わせることができます。
バイオマスエネルギーとしての活用と環境負荷の削減
間伐材の活用方法として、近年注目されているのが「バイオマスエネルギー」としての利用です。
バイオマスエネルギーとは、有機物を燃やすことで得られるエネルギーのことで、間伐材はその主要な供給源の一つです。
バイオマス発電は、再生可能なエネルギー源として、化石燃料の使用を減らすために重要な役割を担っています。
日本でも、間伐材をバイオマスエネルギーとして活用する動きが広がりつつあります。
例えば、間伐材を燃料として利用するバイオマス発電所が各地に建設されており、発電所では間伐材を粉砕し、圧縮してペレット状にして燃料として使用しています。
このように、間伐材をエネルギーとして利用することで、再生可能なエネルギーの供給源としての価値を高めるとともに、森林の健全な管理にも寄与しています。
さらに、間伐材を利用したバイオマスエネルギーは、二酸化炭素の排出量を大幅に削減できるというメリットがあります。
木材は育成過程で二酸化炭素を吸収するため、木材を燃焼する際に放出される二酸化炭素は、成長過程で吸収されたものと相殺されると考えられています。
これにより、バイオマスエネルギーは、化石燃料と比べて環境負荷が少なく、持続可能なエネルギー源として重要な役割を果たすことができます。

地域経済への貢献と持続可能な社会の実現
間伐材の積極的な利用は、地域経済の活性化にもつながります。
間伐作業自体が地域の雇用を生み出し、間伐材を利用した製品の生産は、地元の工芸産業や製造業の振興にも寄与します。
例えば、間伐材を使った家具や建材が地元の工房で製造され、販売されることで、地域のブランド力を高めるとともに、地元の職人たちに安定した仕事を提供することができます。
また、間伐材を利用した観光資源開発も進んでおり、木工やクラフト製品を地域の特産品として販売することで、観光業にも貢献しています。
このような取り組みは、地域全体の持続可能な発展に寄与し、地域の魅力を高めることに繋がります。
間伐材の活用は、単に森林資源を有効に利用することにとどまらず、持続可能な社会の実現にも重要な役割を果たします。
森林は二酸化炭素の吸収源であり、間伐を適切に行い、間伐材を積極的に活用することは、気候変動対策にも寄与することになります。
さらに、間伐材を利用することで、森林の健全な成長を促進し、生物多様性の保全にもつながります。
また、間伐材の利用が広がることで、木材産業全体が持続可能な方向へと変化し、環境に配慮した製品が増えていくことになります。
これにより、消費者は環境に優しい選択をすることができ、企業も社会的責任を果たすことができます。
6.まとめ ~私たちにできること~
間伐が行われない森林では、土砂崩れのリスクが高まり、健康な木の育成が難しくなり、水源が枯渇する危険性が増します。
これらは、私たちの生活に深刻な影響を及ぼす可能性があり、適切な間伐が行われることがいかに重要であるかがわかります。
森林を守るために、間伐を進めることが地域社会、環境、そして経済全体にとって利益をもたらすのです。
間伐材の活用は、森林の健全な管理を促進し、持続可能な社会を支えるための重要な手段となります。
家具や建材、バイオマスエネルギー、紙製品など、間伐材にはさまざまな用途があり、その可能性は無限大です。
今後、間伐材の活用をさらに進めることで、環境負荷を減らし、地域経済を活性化させるとともに、持続可能な社会の実現に向けた一歩を踏み出すことができるでしょう。
私たちの小さな選択が、未来の子どもたちに安全で豊かな森林を残すことにつながります。今日から少しずつ、意識を変えてみませんか?

関連記事